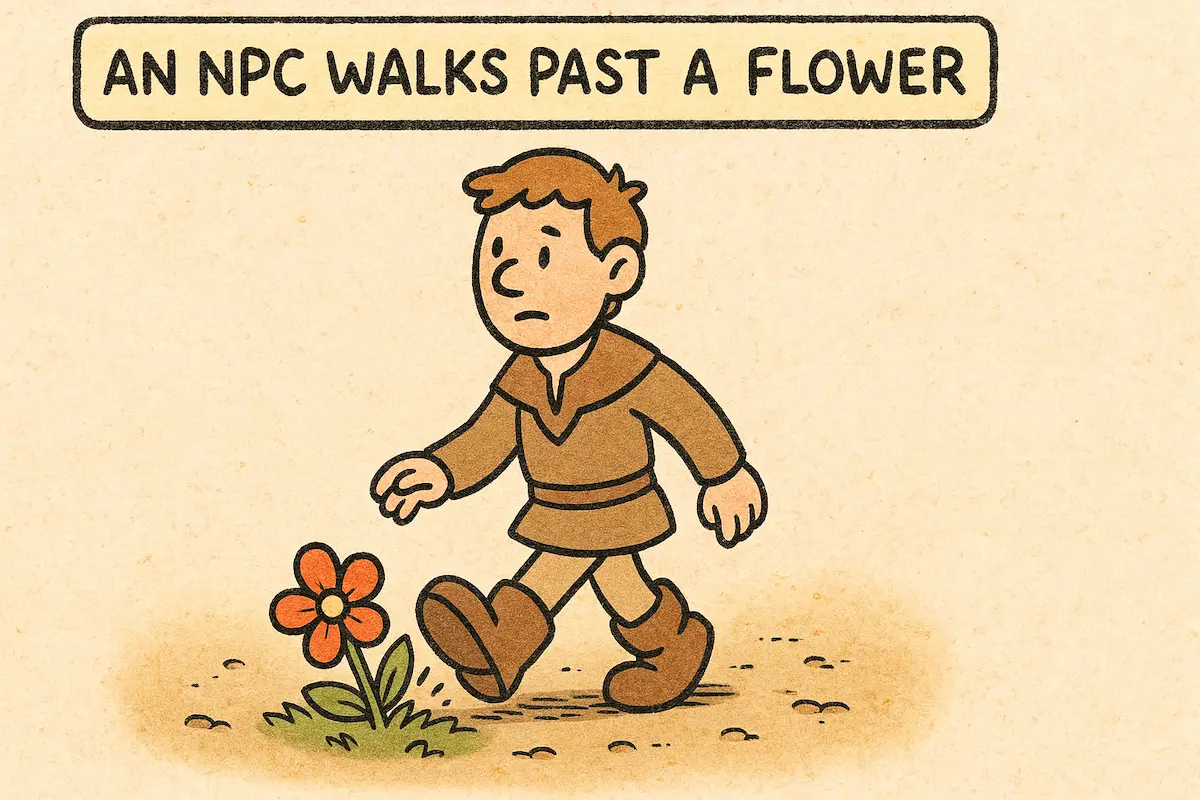オープンワールドゲームの片隅で、NPCが無造作に花を踏みつけて通り過ぎる光景。
誰も気に留めないその瞬間には、システムの冷たさと人間の倫理の限界が凝縮されている。
本稿は、NPCという“非主体的存在”を通して、ゲームデザインに潜む倫理と哲学を読み解く。
第1章 花はなぜ踏まれたのか ― 背景と問題提起
1-1 踏まれる花の光景
あるオープンワールドRPGでのことだ。プレイヤーは村の広場を歩いていた。
遠くに見えるのは、風に揺れる小さな花。そこへ通りかかったNPCが、何のためらいもなくその花を踏みつけ、立ち止まることもなく去っていく。
花は潰れたように見え、やがて草むらに紛れた。
誰も気にしない。ゲームとしては「正常な挙動」だ。
だが、その“誰も見ない違和感”に、小さなざらつきを覚える。
1-2 見られない行為と“非主体”
NPCが花を踏む――それは一見、取るに足らない現象に見える。
けれどもその一瞬には、「誰かに見られることを前提にしない世界の動き」がある。
NPCはプレイヤーに奉仕する存在ではなく、あくまで世界の整合性を保つために存在する“非人格的な仕組み”だ。
その行動の背後には、開発者の判断、AIの制御、そして「観測されない存在」を前提とするゲーム世界の哲学が潜んでいる。
この「踏まれる花」は、現実にも通じる象徴的な出来事である。
社会の中で、無意識のうちに踏みにじられるもの――小さな努力、弱い立場の声、統計の外に追いやられた痛み。
それらもまた、“システムの整合性”の中で忘れられていく。
では、ゲームの世界におけるこの「違和感」は、単なるプログラムの副産物なのだろうか。
それとも、人間社会の倫理的構造を反映する鏡なのだろうか。
ここから先は、ゲームの構造を倫理学的・哲学的に読み解く試みである。
第2章 システムの冷たさ ― ゲームデザインの論理と倫理
2-1 合理的な“無視”
NPCが花を踏む理由は単純である場合が多い。
ゲームデザイン上、NPCの移動経路は「経路探索アルゴリズム(pathfinding)」によって決定される。
彼らは、目的地までの最短ルートを、障害物の衝突判定(collision system)をもとに計算して歩く。
一般的な設計では、花や草などの装飾オブジェクトは“衝突なし/簡略衝突”で扱われることが多い【1】。
つまり、物理的にはそこにあっても、経路上では“ほぼ無視される”対象になりがちだ。
だからNPCは花を踏み越えるように動く。
それは悪意ではなく、意識の外側で起こる自然なシステム的動作である。
ただし、これはすべての作品に共通する仕様ではない。
中には、意図的に花や小物に感情的なリアクションを組み込んだ設計も存在する。
たとえば『The Legend of Zelda: Breath of the Wild』では、花を踏むと花畑を守る女性NPCが怒り出す。
プレイヤーが再び花を踏むたびに、その怒りは段階的に高まり、三度目には激昂してプレイヤーを吹き飛ばすイベントが発生する【1-補】。
このような「行為に対する段階的反応」を設けることで、開発者は“何気ない行動に倫理的な意味を持たせる”仕組みを作り出している。
単なるオブジェクトの回避ではなく、感情の発生を演出するスクリプト構造なのである。
2-2 最適化と倫理のすれ違い
ここには、ゲームデザインがもつ冷たい合理性がある。
開発者にとって重要なのは、「プレイヤー体験を阻害しない動作」と「CPU負荷の最適化」だ。
NPCが花を避けるようにプログラムすることは可能だが、そのためには相応の計算・設定コストが必要になる。
その結果、多くの現場ではシステムの安定性と効率を優先して、花を“無視する”設計が選ばれやすい。
それが、効率的かつ安全な判断とされるからである。
だが、この「合理性」こそが問題の核心である。
NPCが花を踏むという現象は、システムが“意味を持たない存在”を切り捨てた結果でもある。
花は「報酬」でも「障害」でもない。したがって、存在していても、システム上の意味を与えられない。
これをIan Bogost(2007)は『Persuasive Games』で「手続き的レトリック(procedural rhetoric)」と名づけた【2】。
すなわち、ゲームはルールそのもので価値観を表現するメディアである。
花が踏まれる仕様であること自体が、「無意味な存在は考慮されない」という価値判断をプレイヤーに内面化させてしまう可能性がある。
開発者が“見捨てることを選んだ存在”――それが花である。
彼らは、バグでもエラーでもなく、システムの「仕様」によって踏まれる。
そのことに気づくと、プレイヤーは一種の倫理的違和感を覚える。
それは単なる驚きではなく、「意味を持たない行為を前にした不安」だ。
そしてこの冷たいシステムの中で、私たちは問われる。
合理性を追求するあまり、「感じる余地」や「想像の余白」を削ってはいないか?
ゲームに限らず、現実社会のあらゆるシステム――アルゴリズム、官僚制度、経済合理性――もまた、同じ構造の上に成り立っている。
花は踏まれるように設計され、私たちはそれを“仕方ないこと”として受け入れてしまうのだ。
第3章 観測されない存在の意味 ― 哲学的・人間的考察
3-1 顔なき他者と倫理の死角
NPCに踏まれる花は、誰にも見られない出来事である。
プレイヤーが見ていようが見ていまいが、花は踏まれ、そして消える。
そこには「観測者の不在」という深い哲学的問題が潜んでいる。
レヴィナスは『全体性と無限』(1961/英訳1969)で、「他者の顔を見つめることが倫理の始まりである」と述べた【3】。
ただし、NPCや花には「顔」がない。彼らは他者として現れにくい。
ゆえに、倫理の契機が生じにくい。私たちはその存在を“モノ”として扱うことに、ほとんど罪悪感を持たない。
それは、倫理の死角であり、デジタル世界の冷たい構造そのものだ。
ここで留意すべきは、NPCや花に倫理的主体性を直接的に帰属させることはできないという点である。
彼らは痛みを感じることも、意図を持つこともない。
だが、それにもかかわらず私たちはそこに「何かしらの感情」を読み取ってしまう瞬間がある。
それは悲しみであることもあれば、違和感、可笑しさ、怒り、あるいは単なる好奇心であることもある。
この“感情の投影”こそが、人間的倫理の出発点であり、同時に想像力の働きそのものである。
つまり、倫理とは対象の実在的苦痛に依存せず、私たちの想像力が他者を成立させる力に基づいている。
3-2 “感じてしまう”という経験
この「顔なき存在」を考えることは、人間の感受性の仕組みそのものを問う行為でもある。
AIやNPCには「痛み」や「悲しみ」はない。
だが、私たちはそれらに“何かを感じてしまう”瞬間がある。
たとえば『The Last of Us Part II』(2020)では、敵NPCが仲間の死に名前で反応し、プレイヤーに複雑な感情を喚起する【4】。
あるいは『Detroit: Become Human』(2018)のアンドロイドが涙を流すとき――そこに本物の痛みがあるかどうかではなく、「痛みを感じるように見える」ことが、私たちの情動を動かす。
重要なのは、「感情が実際に存在するか」ではなく、「私たちがどこに感情を見出すか」である。
NPCに踏まれる花を見て、悲しみや滑稽さ、あるいは倫理的違和感を覚えるなら、それはプレイヤーの感受性が、システムの外側にまで拡張されている証拠である。
言い換えれば、これは「感情と倫理のシミュレーション」だ。
私たちは、無意味に見える行為の中に“意味”を投影する存在として、ゲーム世界を通じて自らの倫理を再演している。
3-3 社会との鏡像関係
そしてこの構造は、現実社会の縮図でもある。
都市の路上で、誰にも気づかれずに散っていく花。
SNSで流れていく悲鳴。
効率化と最適化の名のもとに切り捨てられる小さな存在。
それらを「見ないふり」する社会において、私たちはすでにシステムのNPCなのかもしれない。
ただし、この比較はあくまでアナロジーであり、現実の倫理問題とゲーム設計を直接同一視することはできない。
ゲームの中の“行為”は象徴的な構造として存在し、そこに倫理的洞察を見出すのはプレイヤーの想像力である。
この区別を明示することによって、「ゲームが倫理を映す鏡である」という主張が、より慎重で説得的なものになる。
ゲーム内で踏まれる花は、実は私たち自身の姿を映している。
人間中心主義の視野から抜け出せないまま、無数の“非主体”を踏みつけて進む――
そんなデジタル時代の無意識が、そこにある。
第4章 悲しみをデザインする ― 実践・応用・展望
4-1 共感のデザインと倫理的世界観
ゲームにおける「感情」は、必ずしもストーリーや演出によって生まれるものではない。
むしろ、それはシステムの隙間――ルールの無音地帯に生まれる。
NPCに踏まれる花のように、「誰も意図していない感情」こそが、最も人間的な体験を呼び起こすのかもしれない。
近年のゲームデザインには、「共感のデザイン(Design for Empathy)」という新しい潮流がある。
例えば『Journey』(Thatgamecompany, 2012)は、テキストもボイスもない中で、匿名のプレイヤー同士が簡素な発声(チャイム)で協働する“無言の共感”を描いた【5】。
『Death Stranding』(小島秀夫, 2019)のSocial Strand Systemは、他者の残した橋・標識・道路等を非同期的に可視化・共有する設計で、**“誰かの足跡が自分を支える”**という倫理をシステムに直結させた【6】。
これらの作品は、直接的なストーリーテリングではなく、システムそのものに倫理や情動を埋め込む試みと言える。
重要なのは、「感情を排除すること」ではなく、「感情に気づけるような構造」を作ることだ。
NPCが花を踏まないように設計することは技術的に可能だが、それでは“無関心の構造”を可視化する機会を失う。
むしろ、踏まれてしまうその瞬間をあえて残すことで、プレイヤーに“気づく余地”を与えることができる。
この「気づきの余白」こそが、共感を生み出すデザインの中核である。
なお、同様の“気づきの遅延”を、日常的な文化儀礼の側面から描いた報告書として、
『冷やし中華、始められなかった — 季節的儀礼の崩壊と主体消失に関する報告』 がある。
そこでは「始まらない」という現象を通して、社会が“感じることを後回しにする構造”を分析している。
ゲーム世界で踏まれる花と、現実世界で始められなかった冷やし中華。
どちらも、**「システムに組み込まれた感情の欠片」**として響き合っている。
第5章 本稿の結論
NPCに踏まれる花――それは単なるプログラムの挙動ではない。
そこには、システムの合理性と人間の感情が交差する境界がある。
私たちは、ゲームの中で「意味のない行為」に出会うとき、システムが持たないはずの倫理や情動を感じ取ってしまう。
その違和感こそ、人間の想像力の証である。
開発者にとって、花を踏むNPCは“仕様”にすぎない。
だがプレイヤーがその光景に何かを感じるなら、そこに「倫理的体験」が発生している。
つまり、感情はシステムの欠陥ではなく、人間性がシステムに反射した瞬間なのだ。
ゲームの中で踏まれる花は、現実社会における“見えない他者”を象徴する。
アルゴリズムが効率を最適化し、経済が合理性を追求するほど、私たちは“意味を持たない存在”を見落としがちになる。
だが、たとえシステムが無関心であっても、人間の感受性はそれを超えることができる。
プレイヤーが花に目を留め、何かに気づく瞬間――それは、倫理が再起動する瞬間である。
本稿の結論:
NPCに踏まれる花は、デジタル世界の冷徹なシステムの中に残された「人間性の余白」である。
その小さな出来事に気づくことこそが、AI時代の倫理的想像力を取り戻す第一歩だ。
“踏まれる花”を見過ごさない感性――それが、システムの外にある唯一の自由なのかもしれない。
参考文献
【1】 Epic Games, “Open World Tools Property Reference,” Unreal Engine Documentation, accessed 2025-10-17.
(“Typically, this will be enabled for small meshes without collision (e.g. grass) …”)
【1-補】 “Watch Out for the Flowers,” The Legend of Zelda: Breath of the Wild (花を踏むたびに怒りが段階的に上昇し、三度目で攻撃。参照:Zelda Wiki, Zeldadungeon)
【2】 Bogost, Ian. Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. MIT Press, 2007, pp. 29–47.
【3】 Levinas, Emmanuel. Totality and Infinity: An Essay on Exteriority. Trans. Alphonso Lingis. Duquesne University Press, 1969(原著1961), p.198.
【4】 Makuch, Eddie. “The Last of Us 2 Makes Killing Enemies Even More Personal, Developer Explains.” GameSpot, 28 May 2020.
【5】 Thatgamecompany. “Journey Comes to PSN Today.” PlayStation Blog, 2012.
【6】 TIME. “What Hideo Kojima Wants You to Learn From Death Stranding.” TIME Magazine, 8 Nov 2019.